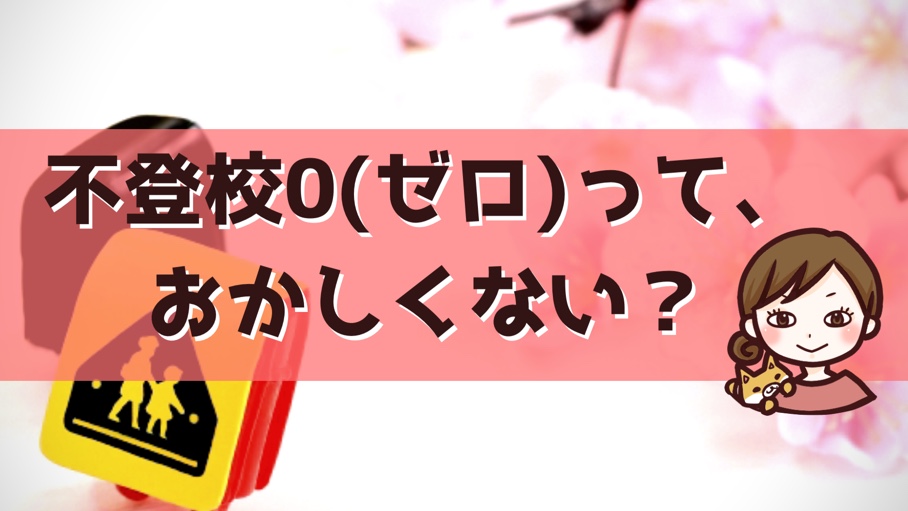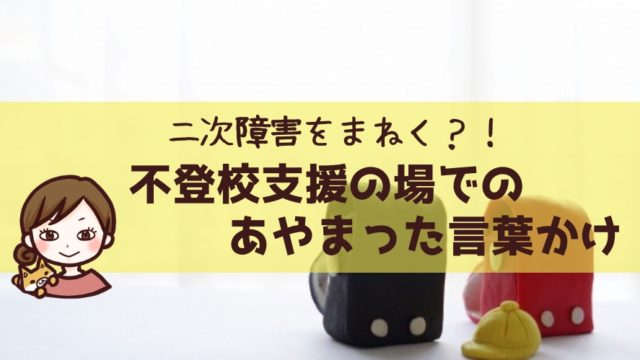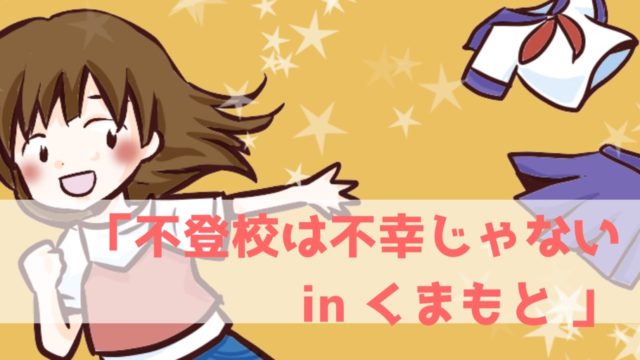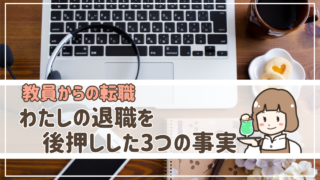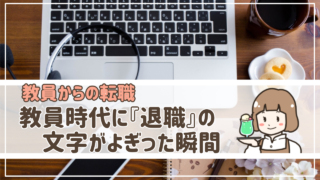『多様性』という言葉を耳にすることが増えたのと同時に、不登校の実態も非常に多様化していることを肌で感じます。
ここ数年は、不登校対応の放デイや相談機関に務めたり、学校現場でスクールカウンセラーをしていたりしていることもあり、本当に『不登校』という言葉でひとくくりにすることが不可能なくらいさまざまなケースに出会います。
そもそも『不登校』って?

ちなみに不登校の定義は…
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由を除いたもの
だそうです。
この30日以上というのが、現場は結構気にするところだったりします。
学校に行ったり行かなかったりする子の場合だと、いかに欠席が30日を超えないようにするか、という点に執着し、あの手この手を使って登校刺激をされることもあります。
なんで30日にこだわるかっていうと、単純に報告義務があるからです。
教育委員会や教育事務所など、その地域を管轄している行政に対し、不登校の子がいるということを学校は報告しなければいけません。
ただ、それだけです。
最近では、ある意味『不登校』が一般的になり(それもどうなんだと思うのですが。)、先生たちも現状を受け入れ、過剰な登校刺激はだいぶ抑えられていると思います。
しかし、実態が多様化しているだけに先生方からは「どう接していいのか分からない。」「どの程度の関わりなら大丈夫なのか分からない。」という声も多く聞かれます。
誰にでも「苦手な場所」「合わない場所」がある。
私の知人に、ディ○ニーランドが嫌いという人がいます。
あの「夢の国」です。お金を積まれても行きたくないそうです。
理由は、看板キャラクターの踊るイケメンネズミが嫌いだから(笑)
そんな「夢の国」って言われている場所ですら、嫌い、行きたくないという人がいるのです。
学校が嫌い、合わない、行きたくない、という人がいても全然おかしいことじゃないですよね。
むしろ、学校嫌い、合わない、行きたくない、という子が一定数いるのは正常なことだと思うのです。
旅行先を選ぶのなら、ディ○ニーランドじゃなくて浅草行くか、とか他の選択肢がたくさん思いつくわけです。
しかし、特に義務教育のうちは通う学校は家のある場所によって決められてしまいます。学校も先生も選べません。

そして、不登校の子が増えているということは、現代の子どもたち、ひいては社会の実態に学校現場のスタイルが合っていない、ことが考えられます。
合う場所がなく行き場を失う子どもたち
学校が合わなくて結果的に『不登校』という選択肢を選んだとしても、家以外に居場所は必要です。
勉強をしたり、子ども同士で遊んだり…集団の中で身につく社会的スキルは、大人になったときに必ず必要です。
居場所として考えられる場所
◇フリースクール
◇不登校対応の放課後等デイサービス
◇学習支援センターなど
◇適応指導教室
不登校の受け入れ先も増えてはきましたが、十分とはいいがたいのが実情。

フリースクールは月謝が数万もするなど通い続けるのが難しかったり、特色が強すぎて結局合わなかったりなどの話も聞きます。
放課後等デイサービスは、利用日数や時間が決められていて毎日の利用が難しい場合もあります。
学習支援センターなども中心部にあることが多いため、送迎が必要だったり交通機関を乗り継いで通う必要があったりするため、一部の子どもたちにとっては通うハードルが高い場合があります。
また、フリースクールや放課後等デイサービスは経営状況の悪化などで閉所してしまう可能性なども0ではありません。
自分に合う場所が見つからない、または見つかっても通い続けることが難しいなどの理由で、結果的にほぼ自宅に引きこもって過ごす子どもたちも多いです。
結局は公教育の仕組みを変えることが必要
いろんな不登校の子と出会って、『こんな風に学校がかわれば、不登校も減ると思うんだけどな~』と考えることがあります。
公教育のここを変えてほしい!
◇始業時間を1時間遅らせてほしい。
◇学習内容を選べるようにしてほしい。
◇一日の授業のコマ数を減らしてほしい。
◇一クラスの人数を25人くらいにしてほしい。
おそらく、上記の対応をすれば不登校はぐっと減ると思っています。
どれか一つ選ぶとしたら、一クラスの人数かな…。
学校現場や政策の動向を見る限り厳しいんでしょうけど、この思いが届くことを切に願っています。
『不登校』について思うこと。
もちろん、「幸せ」でも「不幸」でもありません。
しかし、やっぱり社会生活に必要な知識やスキル、将来自分で稼ぐためのスキルや知恵は身に着けていく必要があります。

『不登校』が受け入れられ、支援先も一見多様化した中で、今度はそこから『自分に合う環境を選ぶスキル』が求められているのが現在の状況だと思います。
予定より少し早めに就職活動をすることになったような感じでしょうか。
とにかく、子どもの現状をしっかり理解して、地域資源や社会的なサポートも上手に活用しながら、使えるものはなんでも使う姿勢が大切です。
保護者の方は、ぜひ家族の中だけで悩まず、学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、自治体の相談窓口などを活用してみてください。
一緒に、子どもたちに合う場所を見つけることや、学校を子どもたちに合う場所に変えていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
◇柴ゆきのつぶやき◇
ディ○ニーランドの話を例で出すと、「いやいや小・中学校は義務教育だから。」という反論をされる方がいらっしゃいます。が、他の記事でも書いてますが、子どもにあるのは「教育を受ける権利」であって、義務ではありません。そのあたり理解していただきたいです。^ ^