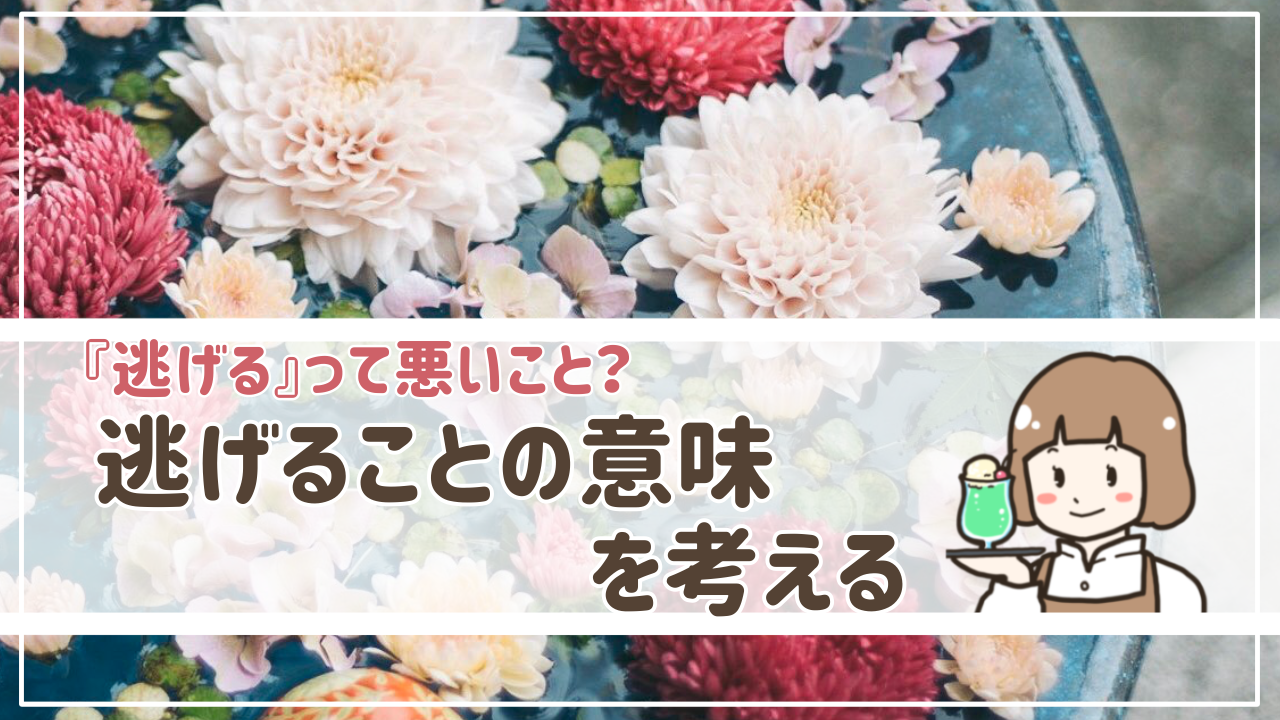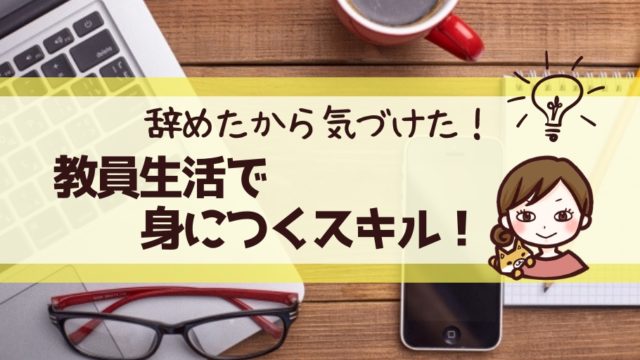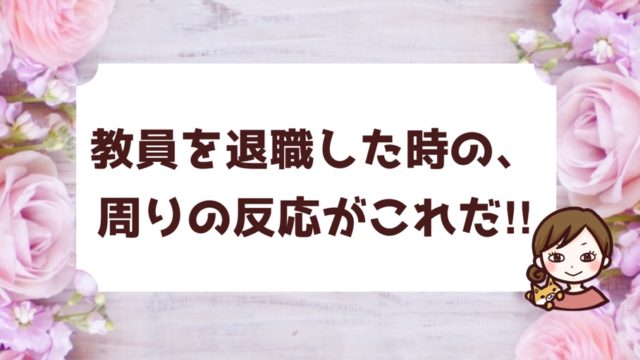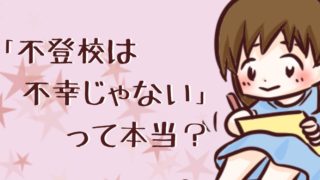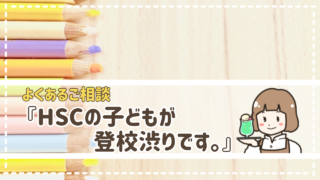突然ですが、みなさんは『逃げる』という言葉にはどんなイメージをお持ちですか?
おそらく思い浮かぶイメージはネガティブなものが多いのではないかと思います。
『逃げるな』『逃げたら負けだ』など、どちらかと言うと『逃げる』のは悪いことだと刷り込まれている人が多いのではないでしょうか。
生き物はどういうときに『逃げる』のか。
わざわざ言うまでもないかもしれませんが、野生動物は危険を感じると逃げます。
身の危険…つまり、「命の危険」です。
命が危機にさらされていると、脳内のサイレンが鳴ります。
厳密にいうと『闘う』か『逃げる』かの選択を迫られるのです。(『闘争』か『逃走』か)
では、人間はどうでしょうか。
本能レベルでは「逃げたい」と思っている状況は、本人にとっては生命を危ぶまれるかもしれない『危機』に陥っている状況である可能性があるわけです。
本来なら『逃げる』選択肢もあるはずなのに、『逃げてはだめだ!』と理性で抑え込み『闘う』ことを選ぶことが往々にしてあります。
「死ぬほどじゃない。」のに逃げていい?
「命に直接関わらないから」と言って、あらゆる理不尽が我慢できますか?
「命に直接関わらないから」上司のパワハラを受け入れますか?
「命に直接関わらないから」睡眠時間削って残業しますか?
「命に直接関わらないから」意味のない職場の習わしに付き合いますか?
でも、それって、あなたの時間や生命力をものすごく消費しませんか。
消費ならまだしも、ただただエネルギーの無駄遣いをしているだけの「浪費」状態になっていませんか。
確かに、直接命を奪われる事態にはならないかもしれませんが、少しずつ生命力を削り取られている状態です。
また、心では「逃げたい」と思っているのに、それと逆の行動をとることは、車でいうと「ブレーキとアクセルを一緒に踏んでいる状態」です。つまり、
「ブレーキとアクセルを一緒に踏んでいるのと同じ状態」っていうのは、鬱や適応障害の説明の際にもよく使われますね。
とても分かりやすく、それがどれほど危険な状態なのかがイメージしやすいフレーズです。
ただ、人間って「自分が壊れるとき」を正確に把握することができないんじゃないか、って思うんです。
「まだ、大丈夫。」「自分に限って鬱なんて。」って思ってしまい、気づいたときには「逃げる」っていう思考すら出来なくなっていることが多いようです。
だから、「逃げたい。」と思ったとき…そう自分で判断できるときに、逃げた方がいいのです。
「逃げる」=「悪いこと」という刷り込みがある。
冒頭に書いたように、「逃げる」という言葉には、どちらかというとネガティブな印象があります。
ですが、自然界の例を見れば分かるように「逃げる」ということは、自分の身を守るために必要なこと。脳にプログラミングされた生存本能なのです。
では、それと逆の認識は、私たちの中にいつ芽生えるのでしょうか。
多くは、成長するまでに身に着けてきた価値観の影響でしょうから、人によって親だったり先生だったり、習い事のコーチだったり…育った環境によるものが大きいとは思います。
「あきらめるな。」とかの、ポジティブな励ましは(百歩譲って)まだいいとして、「すぐ諦めるから、できないんだ。」「ここで辞めるは逃げだ。」などの言葉は、指導ではなく脅迫です。
終いには「心が弱いからだ。」と言われる始末。
(心理職としては、心は強くするものではなく、やわらかくしなやかにするものだと思っています。)
自分の人生を振り返ってみても、上手な逃げ方を教えてくれた大人はいません。
みなさんはどうでしょうか?(いる人はめちゃくちゃラッキー!!)
だれも教えてくれないということは、自分でやってみて上手になっていくしかないことなんですね。
「逃げたい」と思えるうちに、逃げよう!!
「逃げたい」そう、冷静に判断できるうちに逃げることって、自分へのダメージを最小限に抑えるためには、とても大切なことです。
鬱などの適応障害を発症すると、数ヶ月〜数年以上という長いスパンで苦しむことになるからです。
たまに「逃げ出すのはいつでもできる!」と言って止める人がいますが、そうだとしても「逃げるのにベストなタイミング」っていうのも確実にあります。
それが見極められるのは、「逃げる」という経験をたくさん積んだ人ではあるのですが…。
仕事なら、次の仕事を見つけてから、または目処をつけてから辞めましょうってことですね。^ ^
逃げたあとに後悔することもあるかもしれませんが、その後悔は『行動を起こしたゆえの後悔』なので、きっと学ぶことが大きい後悔のはず。
次に『逃げたい』と思ったときに、『闘う』『逃げる』以外の選択肢をもたらしてくれる場合もあるでしょう。
その経験は無駄にはなりません。
今日のまとめ
◇逃げるのは、自分の身を守るために必要なこと!
◇逃げたいのに逃げないのは、エネルギーを浪費しているのと一緒。
◇「逃げたい」と思った時が逃げるタイミング!
以上「『逃げる』って悪いこと?」というタイトルでお届けしました。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。(*^_^*)
◇柴田のつぶやき◇
ちょっと視点を変えて、歴史の話。^ ^
幕末に活躍した桂小五郎は、別名「逃げの小五郎」と呼ばれ、ときには乞食に変装するなど、ありとあらゆる手段を使い「逃げ」ました。しかし、最終的に桂小五郎は明治維新後、木戸孝允という名で活躍し、新たな時代を築く一翼を担いました。なぜ、桂小五郎は逃げたのか。…他でもない「志(こころざし)」のためです。「より良い日本を。」という一心から、自分の身が危険にさらされると積極的に逃げました。逃げて、再起を見計らっていたのです。「逃げ=恥」という武士の文化が浸透していた時代に、桂は異色の存在だったと思いますが、現代においても彼の姿勢からは学ぶことが多い気がします。